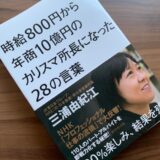前回の記事で、
「時給800円から年商10億円のカリスマ所長になった28の言葉」
という本をご紹介しました。
▽前回の記事はこちらから
【時給800円から年商10億円のカリスマ所長になった28の言葉】クレーム対応の3つのポイントと、【モンスタークレーマー撃退法】
この作品は本作の著者である三浦由紀江氏の、パート時代から管理職までの、現場での様々なご経験やノウハウが語られているものとなります。
目次
明日死んでも、構わない
著者は本作の中で、何度も何度も
「明日死んでも構わない」
という言葉を使っています。
この言葉は、目先の物事に100%全力で取り組んでいることを表しているからこそ、吐ける言葉だと思います。
圧倒的に結果を残すひとの、共通している姿勢
三浦由紀江氏は、本の中で何度も「明日死んでも構わない」と伝えられており、
またその精神は、管理職に就いた今だから発言しているものではなく、
パート時代から、毎日その気持ちを持って物事に取り組んでいたと語られています。
この発言は、僕が東京時代にお世話になっていた会社の社長も全く同じで、
結局、圧倒的な成果を残すひとは、
その姿勢が土台にあるから、
結果も後からついてくるんだろうな。
と、どこか腑に落ちました。
スティーブ・ジョブズの名言
世界一有名な実業家・起業家といっても過言ではない、故・スティーブ・ジョブズ氏の名言は数あれど、特に語り継がれている言葉のひとつとして、次の発言もあがってくるだろう。
もし今日が人生最後の日であったなら、今やろうとしていることは、本当に自分がやろうとしていることだろうか。
この言葉も、先に伝えた「いつ死んでも構わない」の精神をもって
物事に取り組む姿勢を表している発言だろうと推察できる。
大多数のひとはなぜ、「今」を、大切にできないのか
「明日死んでも構わない?」
こう質問されたら、「もちろん」と、このように答えられるひとは少ないだろう。
僕だって、もっともっとやりたいことも、やり残していることもある。
できるならば、過去に戻ってやり直したいことだって何個もある。
一方で、毎日「完全燃焼」しているひとは、明日死んでも構わないと考えている。
「死にたくない」と考えている僕たちは、一生懸命生きていないからなのかもしれない。
結果は後からついてくる
僕はおそらく、一般的なひとよりも割と多くの書物を読み漁っている方だと思う。
本を書いている方々は、何かしらの専門家だったり、研究者だったり、実業家だったり。
共通しているのは、多数の方々から支持されている、「価値あるひと」ということだろう。
そんな方々の作品を読んでいくと、実は本を書いているような方々も、それほど一般的なひとと比べて、大きくかけ離れた能力や才能が存在したわけではないということが、理解できていく。
結局、目先の課題に一生懸命取り組んでいたら、結果として数字がついてきた。
とか。
諦めないで続けてきたから、花が開いた。
とか。基本的にはそんな話が多い。
誰も、特別ではなかった。やろうと思えば、実は誰でもできることなのかもしれない。
結局、目先の物事に本気で取り組めるのかどうかで、人生は大きく変わるんだろう。
漠然と続いていく人生
短距離走だとわかっていれば、誰でもペース配分なく全力疾走できる。
しかし、僕たちの人生は、いつか終わりはくるけれど、それでも「漠然と続いていく」ことが前提にある。
だからどこかで、走り方にペース配分をしてしまう。
予期せぬ余命宣告を受けてしまい、唐突に自分の人生の期限が明らかになったとき、
多くのひとが「こうすればよかった。ああすればよかった。なんでもっと・・・。」と後悔を感じてしまうのは仕方がない。
未来は誰にも予測できない。そしてひとは、麻痺する生き物である。
明日、死ぬかもよ
今では、漠然と続いている、当たり前の平和な日々も
時代や環境が変われば、感じ方も大きく変わっていく。
今生きていることが、退屈で、当たり前。
そう感じて、日常に麻痺してしまっている方には、この本をご紹介したいと思う。
▽あした死ぬかもよ?
本作から一部抜粋し
現在の平和な日々からは考えられない
「今日1日を生きられたことにさえ、感謝できる」
そんな日々に生きていた方々の、生々しい記録をご紹介します。
藤井一中尉の特攻志願
戦争末期、妻子持ちであった教官の藤井一中尉(当時29歳)は
「神風特攻隊」として、次々に命を散らしていく、自分の教え子たちに胸を痛めていました。
当時、家庭を持つ将校は、特攻には採用されないのが原則。
教官として、毎日のように特攻兵として採用され、送り出していく教え子を目の当たりにし、
「自分だけ安全な場所で、教えるだけで本当にいいのか」と、自問自答を重ねていきます。
しかし、藤井中尉には妻の他に、3歳になる長女と、生後4か月の次女もいます。
妻である福子さんは我が子を想い、来る日も来る日も、藤井中尉の「特攻志願」を懸命に思い留まらせます。
しかし、それでも悩みぬいた末、藤井中尉の選んだ道は
教え子に対し「お前たちだけを死なせはしない」と、
命を投げ出す特攻の道を選ぶのでした。
血染めの嘆願書
藤井中尉は家族に隠れ、本部に「嘆願書(特攻志願書)」を提出します。
「将校だから」
「面倒をみなければいけない家庭がいるから」
そういった理由で受理されなくても、何度も何度も嘆願書を再提出します。
そして遂には、夫の固い決意を知ってしまった福子さん(当時24歳)も、ある決断をします。
「私たちがいたのでは、後願の憂いになり、思う存分の活躍ができないでしょうから、一足先に逝って待っています」
という遺書を残し、3歳の長女、生後4か月の次女に晴れ着を着せて、親子三人、厳寒の荒川に身を投げました。
妻子の死を知った藤井中尉は、
今度は指を切り落とし、血染めの嘆願書を提出しました。
そしてついに、特攻兵として受理されます。
特攻に向かう前に、藤井中尉が書き残した遺書が残っています。
12月になり冷たい風が吹き荒れる日、荒川の河川に露と消えた命。
母とともに血の燃える父の意思にそって一足先に父に殉じた、哀れにも悲しい、
しかも笑っているように喜んで母と共に消え去った幼い命がいとうしい。
父も近く、おまえ達の後を追って逝けることだろう。必ず今度は父の暖かい胸でねんねしようね。それまで泣かずに待っていてね。
千恵子ちゃん(次女)が泣いたらよくお守りしなさい。
ではしばらく、さようなら。
僕はこの部分を読んだとき、一時的に時が止まったかのように、
心が震えました。
当たり前の日々とは
明日死ぬかもしれない。
そう思えば、今やるべきことは、このままでいいのか。
「あした死ぬかもよ」という作品は
「一生懸命生きる」
そのようなことを考えさせられる本となっています。
環境が変われば当たり前も変化します。
僕たちが現状に慣れてしまい、麻痺してしまった日常に対して
思い直すためには、とてもいい本だと思います。
まとめ
ひとが気付きや成長を重ねる為には、当たり前に対して「まず疑うこと」が大切だと、東京時代、お世話になった社長が教えてくれました。
なぜ、当たり前なのか。何に対してそのように思うのか。その前提には何があるのか。
そのような深堀を続けると、見え方や捉え方が変化するようになり、捉え方が変わると行動も変化する。と教えられたことを覚えています。
今の状態は、過去の方々が、必死に繋いで頂いた「バトン」だという認識を持てば、
退屈で当たり前の日常の捉え方が、少しだけ変わるかもしれません。
僕たちも、次世代に素敵な未来を届けられるように、今を必死に生きることで、バトンを次に繋いでいきましょう。
▽Amazon
▽楽天市場
|
|
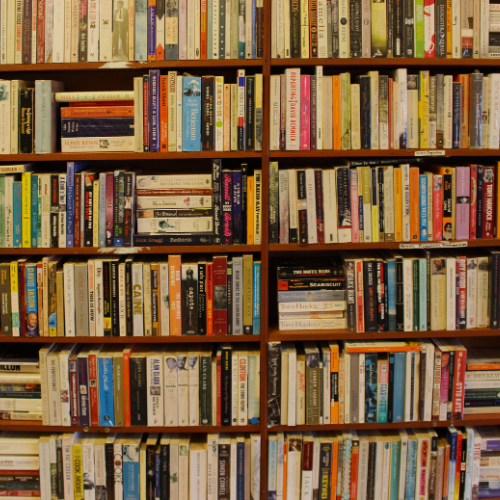 ブログチョップ
ブログチョップ